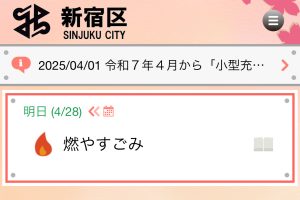こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
次回の一般質問では、分身ロボットの活用について取り上げる予定です。
分身ロボットとは、外出が困難な方が自宅などから遠隔で操作し、ロボットを介してその場に「存在」できるという革新的な技術です。開発者ご自身が不登校の経験を持ち、孤独の解消という理念からこのプロジェクトがはじまりました。
ビデオ会議やメタバースの普及も進む中、あえてロボットという「形ある存在」による参加が注目されるのは、その場にいるという実感が得られること、そして周囲の人々も自然にコミュニケーションを取れることに理由があります。開発者の言葉を借りれば、これは「存在感の質」がまったく異なる体験です。結果として、自己肯定感や社会的なつながりの形成に大きく貢献しています。
私自身、分身ロボットを活用したカフェを訪れました。そこでは障がいのある方が自宅からロボットを操作し、食事を運んだり接客をしたりしていました。単なる実験ではなく、実際のサービスとして成り立っている姿に強く心を動かされました。
行政の現場でも、窓口業務などで在宅の方がロボットを介して働く事例が出始めています。これは外出が難しい方の新たな就労機会となるだけでなく、多様な人材が社会参加するモデルとして今後さらに広がっていく可能性を感じます。
また、教育分野でも注目されています。たとえば、入院中や療養中の児童生徒が分身ロボットを使って授業に参加したり、なんと修学旅行にまで「同行」した事例もあるそうです。学習の機会を確保するだけでなく、友人とのつながりを保つという点でも非常に意義深い取り組みです。
人と人とのつながりを技術が支える。まさに分身ロボットは、その象徴のような存在だと感じています。
それでは本日はこの辺で。