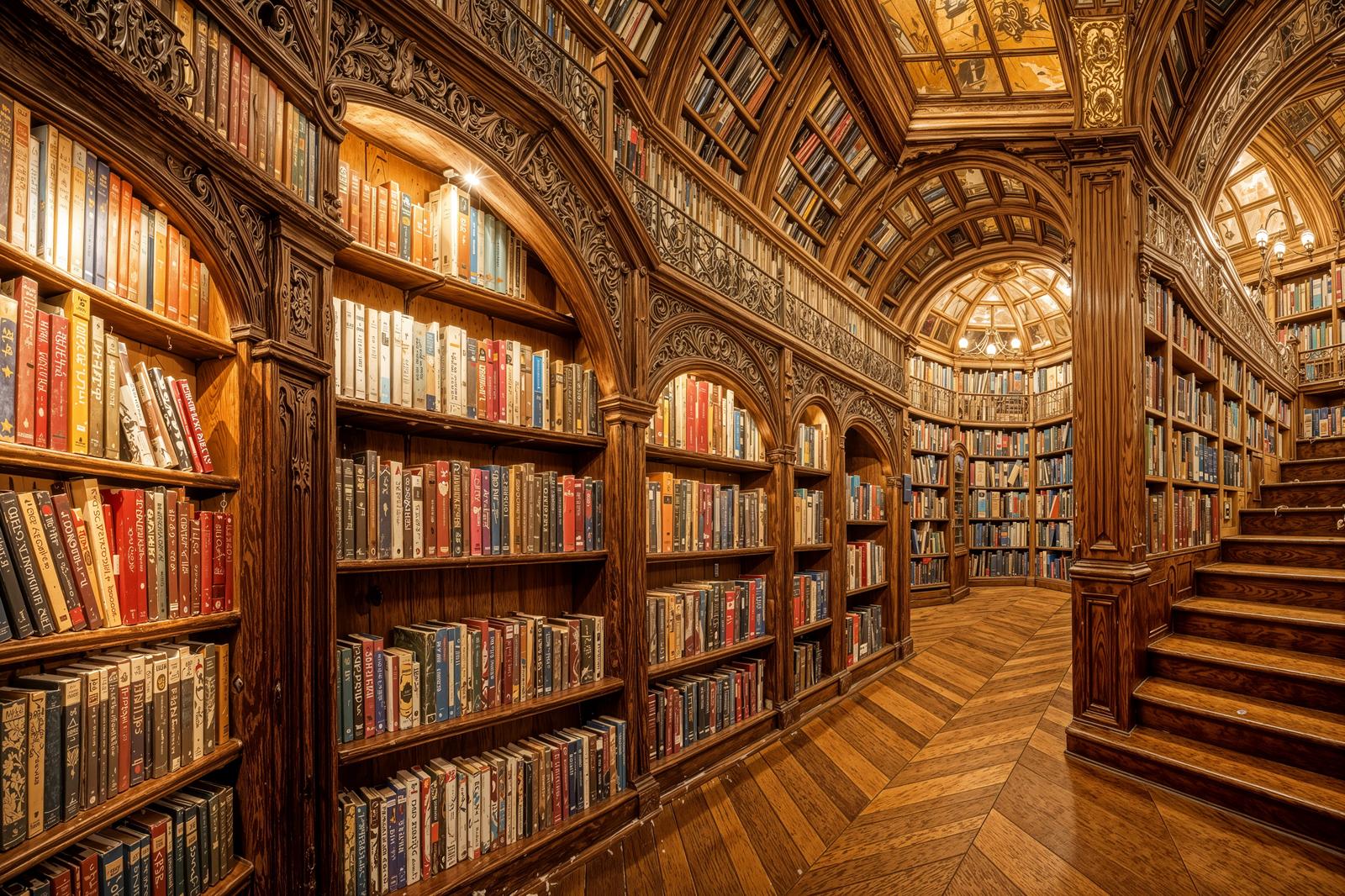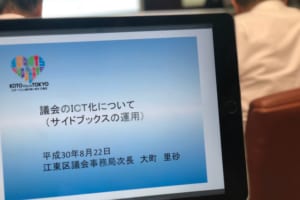こんばんは。新宿区議会議員の伊藤陽平です。
電子図書館サービスについて質問をしました。
昨今では電子書籍や音楽・映像のサブスクリプションサービスが普及し、低コストかつ利便性の高い形で多様なコンテンツを誰もが利用できる時代になっています。月額課金で最新の書籍や雑誌、映像作品にアクセスできる仕組みもあります。つまり、従来図書館が担ってきた「安価に知識へアクセスする機能」の一部は代替されつつあります。
図書館の役割は、理想的には家庭や市場でカバーできない部分を補完する役割に重点を置き、効率的な財政運営と整合させるべきです。この観点で、電子書籍貸出サービスの充実は改革の柱となるDXの施策です。
私自身、新宿区の電子書籍貸出サービスを活用し、名誉区民であるやなせたかし先生の「アンパンマン」を読みました。物理的に図書館へ行かなくても、良質な書籍にすぐアクセスできることは、自治体図書館の合理的な役割の象徴です。時間や場所に縛られないアクセスの仕組みは、図書館のあり方を根本から変える可能性を持っています。
一般的なサブスクリプションサービスのように、電子書籍貸出もデジタルの特性を活かすことができれば、低コストで提供可能だと考えます。将来的には、コスト削減と適切かつ充実した電子書籍へのアクセスが実現できるのではないかと期待しています。
以下、質問と答弁です。
—
伊藤 新宿区の電子書籍貸出サービスについて、運営コストや貸出数、一貸出あたりの単価などのデータは分析されていますか。また、現時点で電子書籍貸出はどのように評価されているのでしょうか。
教育長 令和7年1月15日から開始した電子書籍貸出サービスに関する経費は、令和6年度決算で当初導入費用を含め、1,328万7千円でした。令和7年度は、1年間の運営経費として、システムのランニングコストを含め、1,182万3千円を計上しています。令和6年度の一貸出あたりの単価は、人件費及び初期導入費用を除き2,414円でした。 従来のいわゆる紙の資料については、購入費用だけでなく、貸出をするための装備費用や施設の維持管理経費などを考慮する必要があり、一貸出あたりの単価を算出することは困難です。 そのため、従来の資料との比較はできませんが、令和6年度に選定した電子書籍資料3,461点に対して、年度内の3か月で3,927回の利用実績があったことから、現時点では、区民の利便性向上に成果があったものと認識しています。
—
決算特別委員会はあと明日と明後日だけ残して終盤戦となりました。
時間が足りないときは用意していた質疑を削って運営に協力したいと考えていましたが、特定の各委員に質疑が偏らずに全体的に多くの質疑がされていたと思います。
時間に余裕があれば、教育費で電子書籍のについて発言をしたいと考えております。
今の時点では電子書籍を自分で買った方が安いのではと思えるほどコストが高い点や、今後の事業者の選定や共同調達等による改善に関連することを追加的に伺おうと考えています。
昨年よりもゆっくり進行しているようなので微妙なところですが、どこかの機会でまた取り上げたいです。
それでは本日はこの辺で。